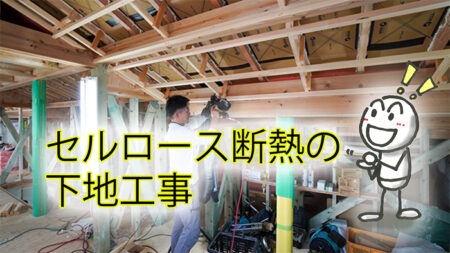スケルトン&インフィル
本日は、富士市の薪ストーブのあるおうちの工事現場からです。

二階です。
手前の扇風機みたいな照明器具が付いている壁も、奥の合板が立て掛けてある壁も、天井工事を先行で作り、後からパーテーションのように間仕切っています。
つまり、構造上強度を持つ壁ではないということです。
下の写真で、赤い部分が、上の写真の合板を立て掛けてある壁です。

以前のブログ「耐震上は耐力壁より床の強度のほうが大事」という記事で、上記の少し前の工事風景をご覧いただけると分かりやすいかと。
構造上、つまり耐震上重要な耐力壁以外は、リフォームの際に簡単に撤去できるよ、としておくと将来の間取りに可変性が出きて、家を長く使うことが出来ます。
それを可能にするために、耐力壁は、できるだけ建物の外周面で確保し、
内部は階段の横など、将来動かさない部分のみで、できるだけ最小限にします。
こういった考え方を、構造(スケルトン)と内部造作(インフィル)を明確に分けて考えることから、スケルトン&インフィルと言います。
鉄骨や鉄筋コンクリートは、もともとスケルトン&インフィル。
イオンなどで専門店間の間仕切りは構造と一切関係ないですよね、あれと同じです。
木造住宅でも、こういった考え方がこれからはとても大事になります。
住宅を長持ちさせるためです。

もう少ししたらご紹介できますが、こちらのお宅では、階段室も入れ子細工のような、ある意味スケルトン&インフィル的な設計です。
そんな階段室になる部分で、電気職人夫妻が奮闘中。

「階段の何段目に立ったときの照明器具の位置が…」
とやっています。
照明の位置は図面に書いてあって現場で悩む必要なんかない、と思われるかもしれませんが、やっぱり現場で「もうちょっと上」「やっぱもう少し右」とかやったほうが、しっくり来ます。
あの有名建築家の堀部さんでさえ、そうされてましたしね…(笑)。
2021年05月13日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。