短命住宅ではいけない
本日は、富士市の建替え現場からです。
まずは解体工事。

ですが、おそらく一般の方がイメージする「解体」からすると、地味な写真ではないでしょうか?

昨今はごみの分別が非常に厳しく、上の写真のように、まずは石膏ボードを手で解体、からです。
当然、重機でグチャより手間ひまがかかり、コストも高くなります。

アルミサッシも手で外されてますね。
昔話では、自分で解体して河原で燃やしちゃった、みたいな猛者もいたようですが、今そんな事したら捕まります。

そうしてやっと重機の登場。
住んでいた人はもちろんですが、工務店の仕事をしていると、作ったた当時の息吹まで感じられる解体現場は、なんとも悲しげな雰囲気を感じてしまいます。
このお宅は築四十数年と聞きます。
上の写真で指差す部分、浴室入り口なんですが、アップすると、

土台は腐り、柱の根元など、無くなって宙に浮いています。
大地震が来ていたら…
そう思うと恐ろしいですね。
このような写真からも、こちらの家は、その寿命を終えていたのでしょう。
家の場合、寿命とは言いません。
生後何年で死んだか=寿命、だとすれば、築後何年で解体されたか=滅失住宅の平均築後年数、と言います。
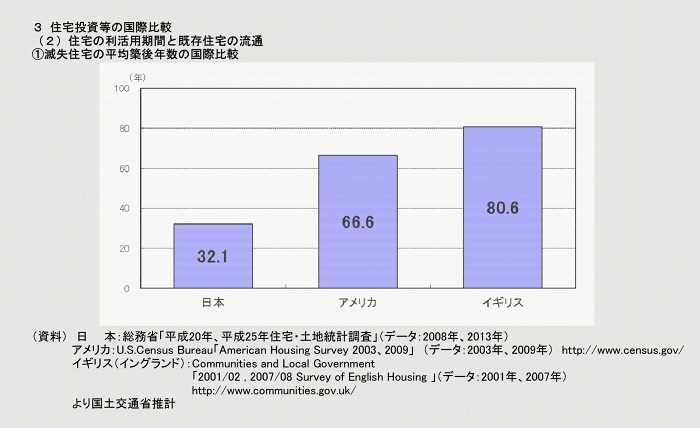
このグラフは、国土交通省のホームページ「平成30年度 住宅経済関連データ」というところからダウンロードしたエクセルファイルを画像にしたものです。
住宅ローンより、日本の家の寿命は短いのです。
諸外国に比べても、なぜこんなに極端に短いのか?
税制の問題や習慣などもあるかもしれませんが、一番は、
【水漏れや結露が家を腐らせるから】
だと思います。
そして、建てる時に、見栄えばかり宣伝して、【耐久性を疎かにする業界の体質】に問題の本質があります。
早く住めなくなって建て替えてもらった方が儲かるから…。
よーーーーく勉強して、長持ちする家、一生住める家、資産として受け継がせることが出来る家、にしましょう!
2019年07月25日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。
















