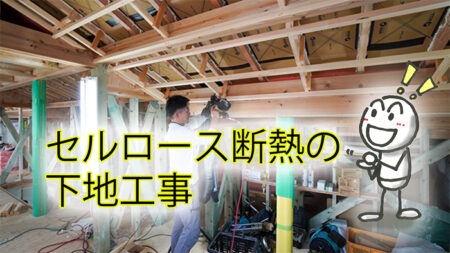iphoneのFLIR ONEを使ってみた
低燃費カーや電気自動車など、いわゆるエコカーが人気なのは言うまでもありません。
「燃費」で計算すると、今使ってるガソリン代を考えると、買い換えても何年で元が取れるね、と言った事が簡単に出来るのも、人気の理由でしょう。
しかも、試乗して使い心地(乗り心地)も試してみることが出来ます。
住宅はどうか…?
「断熱性」が「次世代基準」とか言われても、一般の方にはぴんと来ない。
燃費も分からなければ、住み心地は、住んでみるまで分からない。
が、今や断熱性能は見える時代、比べる時代になってきました。

ネットで話題の、iphoneに合体させて使う熱感知カメラ「FLIR ONE」。
私も持ってます。
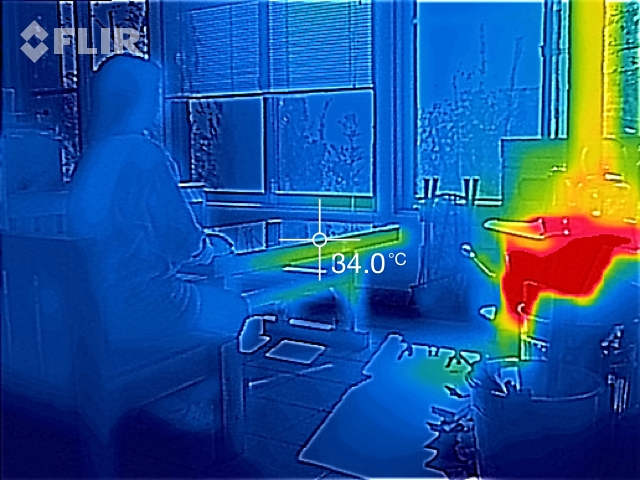
会社の薪ストーブと家内を撮ってみました。
中心部の温度の測定も出来ます。
ストーブがかなり熱いのが分かりますね。
床の日が当たっているところも、形がくっきり出ています。
iphoneのカメラ機能と連動させて、実際の写真画像と合成して出力してくれるので、どこの場所をとっているのかが一目瞭然です。
ちなみに、この画像は縮小しておりません。そのままのサイズ(640×480ピクセル)です。
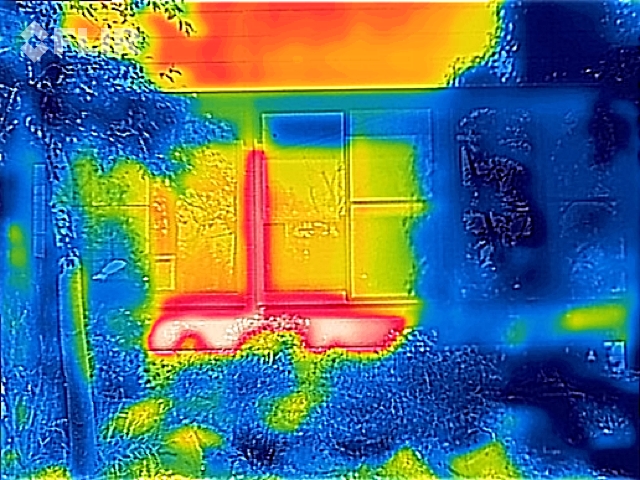
こちら、会社の外壁。
日が当たっているところは赤く、木で陰になっているところは青い。
うん、とてもわかりやすい。
このカメラ自体の存在は一年前のとあるセミナーで知りました。
「こんなカメラが出たら日本中で裁判になるぞ!」
「倒産する建設会社が続出するぞ!」
と建設業界に戦慄が走りました。
なぜか?
そもそも熱感知カメラは、赤外線を感知して、表面温度の違いを視覚化します。
数十万から数百万もする高価なカメラなので、一般には出回っていません。
が、iphoneと合体することで、複雑な演算処理やカメラ機能・表示機能、そういったものは全てiphoneがやってくれるので、大幅にコストダウン。
数万円で手に入ります。
すると、こんな事が起きるゾ!と言われたのです。
「あったか住宅って言われたのに、すごく寒いんだよね…。ほかのうちと比べてどうなのかな…。」
熱感知カメラで見てみたら、
「えっ!他の家より我が家の方が赤く映ってる!熱が逃げてんじゃん!」
とか、
「このiphoneのガジェット、おもしろいね…。ほら、うちの壁も、こんな風に映るよ…。」
熱感知カメラで見てみたら、
「おいおい!ここの部分だけ何でこんなに赤いんだ?ここ、断熱材がちゃんと入ってないんじゃないの!?」
と言った具合です。
まさに、「訴えてやるwww!」ですね。
ただ、使ってみて分かったのですが、温度のレンジ調整機能が無い(私がいじった範囲で見つからない)ので、温度の微妙な違いを見ることは、このカメラでは出来ないようです。
(断熱材を手抜きした業者さん、ご安心を。)
※「レンジ調整はこうやると出来るよ」とご存じの方は、逆に教えて下さいませ
※追記:どうやらアプリ「FLIR tools」で出来るようです(やってみたけど私は分からない…)。
熱感知カメラは、軍事作戦でも大活躍します。
暗闇で熱感知ゴーグルを付ければ、相手は暗闇で何も見えないのに、こちらは壁の向こうに隠れている敵や、数分前に隠れていた場所まで、「画像」として見えてしまうからです。
どーも、その辺の事情(実際、製造元のFLIRは軍事会社)と、エントリーモデルを高機能にするとハイエンドモデルが売れなくなる、という事情から、このihoneのカメラは、あくまでお遊び用に機能を制限しているそうです。

が、冒頭のように、これからは住宅業界でも、車と同じ様に、断熱性能も見える化してゆかなければと思います。
写真は、先日参加したとあるセミナーでの一コマ。
なるほどなるほど…その通りだ。
・現在の高断熱基準は、海外では、欧米はもちろん、中国や韓国でも、まるで通用しない。
・そもそも、現行の高断熱基準は平成11年のもので、義務ではない。
・その基準が、2020年にようやく義務化。
・その時代遅れ?の基準でさえ、半数以上の建設会社はやったことすらない(業界紙調べ)し、
・5年後に義務化されることも、半数程度の会社しか承知していない(業界紙調べ)。
そんななかで、震災後のエネルギー事情を考えて、温暖な静岡でも、北海道並みの断熱性能が必要じゃないか?と取り組んできたマクスとしては、
・お客様に「どれくらい暖かいんですか?」
・燃費はどれくらいですか?
の素朴な疑問に、明確に答えられるようにしよう!
と思っています。
というか、ここに書いているのは、もうその準備は完了しているってことですけどね(笑)。
徐々にブログでもご紹介して参ります。
2015年02月09日
Post by 株式会社 macs
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。