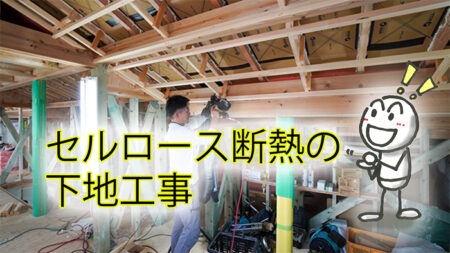モノコック
富士宮市で工事中の、【びおハウスM】の現場の様子をご紹介いたします。
まずは、二階の写真。
.jpg)
中央にドサッとあるのは、プラスターボード、いわゆる壁下地です。
近くで工事中の某ローコストメーカーさんの現場では、この現場で構造見学会をしている頃、工事が始まりましたが、もうとっくにプラスターボードは張り終わっています。
速攻で追い抜かれた社員大工の丸山、顔色変えて奮闘中です。
(ガッツだ!頑張れ!)
中央部の天井には…
.jpg)
以前ご紹介した、「ヒートチムニー」が開いています。
熱の逃げ口・明かりの入口・風の通り道♪
言葉は素敵ですが、この中のプラスターボードの施工はしんどいこと間違いなし(笑)。
(根性だ!頑張れ丸山っ!)
さて、こちらは一階。
.jpg)
別アングルからもう一枚。
.jpg)
こちらで既に貼られている白い壁は、先のプラスターボードではなく、「あんしんN」という、地震に耐える「耐力壁」となる、耐力面材。
許容応力度設計という構造計算によって、外側の耐力面材だけでは不足する部分にのみ、配置してあります。
このへんが、単なる壁量計算だけとの違いですね。
さて、本日のお題「モノコック」。
一階と二階を見ていただきましたが、お気づきでしょうか、内部には、二本の大黒柱である、6寸角の通し柱が有る以外は、柱も壁もありません。
地震に耐える耐力壁は、外周部のみで取り、内部には構造的な物は、この二本の大黒柱のみです。
間仕切り壁は、構造とは無関係で、いわゆるパーテーションとして作られます。
これにより、家族構成の変化によって、自由に壁を付けたり、取ったり、移動したり、が出来るわけです。(ラジバンダリと書かない私は大人さっ)
こういう部分が、住宅の長寿命化に貢献するポイントです。
何にも考えずに家の中の壁をぶち抜いて、「何て事でしょう!こんなに広くなりました?!」とかいうのはダメなんです。
地震でやられてしまいます。
家族の命を守るのが家なんです。
この様に、外周部に応力を受け持たせる構造を、モノコック構造と言います。
車や飛行機も、昆虫やカニさんも、モノコック構造です。
「モノコックが最高!」「モノコック以外は偽物!」
じゃないですよ。
日本の伝統工法の貫構造だって本物です。
大事なのは、ガッチリした構造ってことで。
悲惨な地震を経験してもなお、
四号建築物特例があるから木造住宅は構造計算しなくて良い、
なんて…、
.jpg)
(…誰だ?コイツ)
2012年10月12日
Post by 鈴木 克彦
About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。