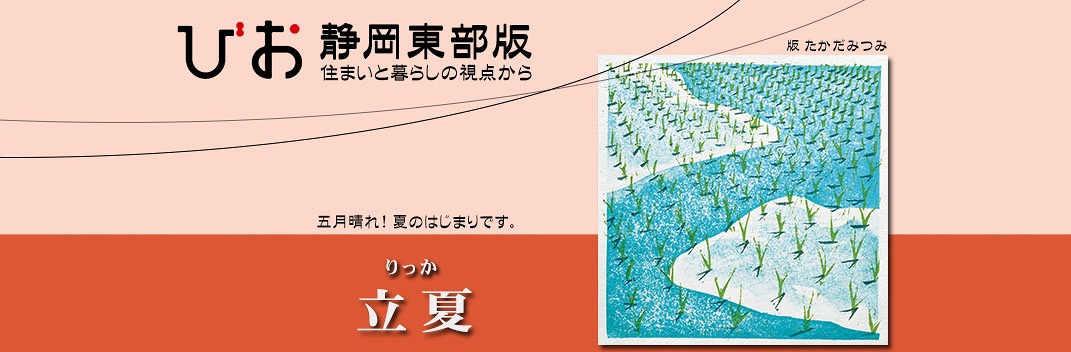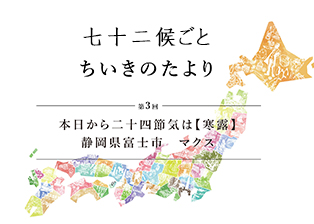大嘗宮の一般参観に行ってきました
本日より七十二候の季節は、大雪の次候「熊蟄穴:くまあなにこもる」。
クマも寒くて冬眠する頃、そんな寒い時期ですが、先日、東京出張に行った際に、大嘗宮(だいじょうぐう)の一般参観に行ってきました。
一般参観の期間は18日間と限られていたので、タイミングよく行くことが出来てラッキーでした。
大嘗宮とは、天皇陛下即位に伴い儀式、大嘗祭(だいじょうさい)の中心的な儀式が執り行われた場所です。
一世に一度の皇室伝統行事とあって、テレビでも度々に取り上げられていましたね。
そんな注目度の高さもあってか、平日にも関わらず、なかなかの混雑具合でした。
富士市より随分寒い東京ですが、みんなでぞろぞろと黙々と、皇居内の東御苑を目指して歩いていきます。
今の時期は紅葉も楽しむことが出来ましたよ。


そして段々と見えてくる、大嘗宮。
想像よりもずっと大きかったです。

木造の建物は大小合わせて30にもなるそうです。
建設を担当した清水建設は、全国各地から宮大工を120人ほど集めて、
なんと3ヶ月あまりでそれだけの建物をつくってしまったのだそうです。

やっと主要部に近づいてきました。
しかし、近づけは近づくほど、混雑は激しくなり、カメラのシャッター合戦がすごい…。
じっくりと見ることはできませんでしたが、仮設とは思えないほど丁寧に造られていたのでびっくりしました。

ものすごい混雑で、カメラもまともに構えられず、斜めですみません…が、ご覧の通り、ちょっと変わった鳥居がありました。
このように皮付きの丸太をそのまま使う工法を「黒木造り」と呼ぶのだそうです。
その他にも、柱に唐松の黒木を使ったり、大嘗祭の祭場となる悠紀殿(ゆきでん)と主基殿(すきでん)の2棟は屋根上に千木(ちぎ)と勝男木(かつおぎ)を備えていたりと、古代の工法そのまま活かした簡素な造りとなっていました。
一般参観が終わると、大嘗宮は、解体され、そしてバイオマス発電用の燃料チップとして再利用されるのだそうです。
これだけの建物をあっさりと壊してしまうのはなんだかもったいない気もしますが、こればかりは仕方がないことですね…。
いつになるか分かりませんが、また次に見れる機会を楽しみにしたいと思います。
文:井出祭子
About Me

住まいマガジン「びお」の、静岡地方版ざます。
工務店のマクスから、家づくりの情報とは違った切り口で、「住まいと暮らしの視点」からローカルで旬な話題を発信してゆこうと思っておりますワン。
ビオブログアーカイブ
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (6)
- 2022年9月 (6)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (7)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (6)
- 2021年12月 (7)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (6)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (6)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (5)
- 2021年5月 (6)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (6)
- 2021年2月 (6)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (6)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (6)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (6)
- 2020年1月 (7)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (6)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (5)